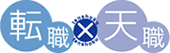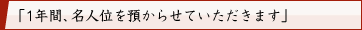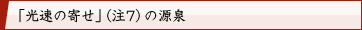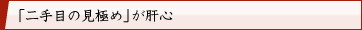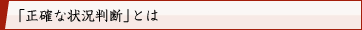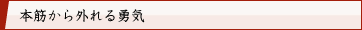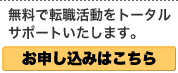谷川 浩司

プロフィール
1962年、神戸市生まれ。11歳で若松政和七段に入門し、14歳で4段となり、異例のスピードで昇進する。史上最年少21歳で名人、92年に4冠、97年には十七世名人になるなど、現在まで将棋界の第一人者として活躍している。

「構想力」
角川書店/
686円
当時の加藤一二三名人を破り、21歳という史上最年少の若さで名人位を獲得したとき、谷川氏が会見で発した言葉だ。この発言からもわかるとおり、人柄はきわめて謙虚で温厚、世間からは人格者として尊敬されている。
名人位獲得後も大舞台を経験し、20代の若さで将棋界を代表する棋士となった。将棋大賞の最優秀棋士賞をはじめとして、大山康晴(注1)、中原誠(注2)、米長邦雄(注3)といった将棋界に名を残す棋士たちに続いて、史上4人目の4冠王になるなど、数多くのタイトルを獲得していった。
ところが、ある若手棋士の登場によって、様相が大きく変わる。その棋士の名は羽生善治(注4)。名人位についたのは谷川氏より遅いが、初タイトルは19歳2ヵ月で竜王位を獲得している。その後、7冠王となり、社会的にも大きな話題となった。
特に、7冠目となったのは、谷川氏が保持していた王将位だっただけに、タイトルを奪われて無冠となったときには、「当時、年下の羽生さんに対して嫉妬心を抱いていた」と回想している。
だが、無冠になった谷川氏は変わった。1年もたたないうちに羽生氏のもっていた竜王位を奪取し、加えて半年後には名人位までも取り返している。見事な復活だった。
現在の将棋界では、「羽生世代(注5)」といわれる30代の棋士たちが中核をなしており、10人いるA級順位戦(注6)のメンバーにおいて、谷川氏は40代でただひとり、それも最年長で活躍している。
この強さを支えているのが「構想力」だ。谷川氏はそれを次のように定義している。
「何かものごとを成し遂げようとしたとき、どうすれば最終的な目標に最短でたどりつくことができるか、置かれた状況やさまざまな条件を考慮しながら、そのための方法と具体的な手順を導き出し、組み立てていくこと」
言葉を言い換えれば、「先をイメージし、見通す力」となる。
現代の世の中は不透明で、どのような未来が待ち受けているか、それをわかっている人はほとんどいない。だからこそ、自分の将来像を描き、それを実現させるために創意工夫し、努力しなければならない。つまり、私たちも「構想力」を身につけることが大切なのだ。
「将棋の一局は序盤、中盤、終盤に分けることができます。一局あたりの総手数は平均すると110手前後です。
序盤は前例のある形で進んでいくことが多く、対局前に準備しておいた構想で乗り切ることができます。あまり構想力を必要としません。
ところが、中盤以降は未知の局面に入っていきますから、構想力が勝負を左右するのです。
プロの棋士ならば、その勝負に勝つためのパターンをいくつかイメージしながら中盤以降を戦います。
私の場合は、他の棋士よりも少し早い段階からその作業を始めますが、その際に自陣を省みることはしません。お互いに一直線に攻めたとき、どちらが勝つかを読むのです。
それによって、相手との距離感がわかってきます。早い段階で勝ちパターンをイメージしておくことで、具体的な手順を構想しやすくなり、より正確にたどりつきやすくなるわけです」
「構想を立てるときにもっとも気をつけなければならないのは、『二手目の見極め』です。自分がこう指したら、相手がどのように指してくるか、それを深く正確に予測します。
将棋の初心者の方は三手目の読みができないとよく言われますが、それは二手目の判断が甘いからです。
初心者の方はどうしても自分にとって都合のいい手しか読もうとしません。『こう指してくれたらいいな』ではなく、『こう指されては困るな』という手を読まなければなりません。そうでないと、正しい構想は立てられません。
構想を立てるときは、相手の立場で想像することも必要なのです」
「将棋では『香車4枚を見ろ』とよくいわれます。最初、香車は盤の四隅に置かれていますが、『盤面全体を視野に入れなさい』という意味なのです。
自分が攻めに夢中になるあまり、その部分では得をしていても、全体では損をしていることも少なくありません。
『木を見て森を見ず』ともいいますが、『大局観』をもてといってもいいでしょう。
そこで、形勢判断をするとき、私は頭の中で盤をひっくり返すことがあります。相手の立場に立って形勢を改めて見てみるのです。すると、自分が苦しいと思っていた局面が、相手も苦しいと気づいたり、その逆だったりすることもあります。これによって新しい構想が生まれることもあるわけです」
「棋士なら誰もが考える手のことを本筋といいます。何が本筋かがわからないとプロの棋士にはなれませんが、本筋しか指せない人、本筋から外れられない人は絶対トップには立てません。
例えば、私は関西在住ですが、東京へ行くには新幹線か飛行機を使います。これが『常識』です。
もし、新幹線が事故で不通になったとしましょう。それにより羽田行きの飛行機は満席になりました。さて、どうしますか。
『常識』的な方法しか考えられない人はそこでパニックになってしまいます。でも、方法はいくらでもあるのです。一度、仙台なり新潟なりに飛んで、そこから新幹線で東京へ行く手もあります。
また、最近はカーナビに頼ることが多く、カーナビが故障したら、どこへも行けないという人も出てきました。カーナビがなければ、『常識』的には幹線道路を行こうとしますが、誰もが知っている道ですから、渋滞している可能性があります。それでは時間に間に合いません。そこで、抜け道や人が知らない道を選ぶ必要が出てきます。
タイトルを獲れるのは、新幹線や飛行機が使えなくても東京へたどり着ける、カーナビが壊れても目的地に到着できる、目的地までの道をイメージできる、そのような人なのです。
常識外の手を構想する力は、新しい未来を切りひらく力ともいえるでしょう」
- 注1 :
- 15世名人。数多くの記録をもつ。将棋界では初となる文化功労者に選ばれている。
- 注2 :
- 16世名人。24歳で大山氏から名人を奪い、「棋界の若き太陽」と呼ばれた。
- 注3 :
- 永世棋聖。現日本将棋連盟会長。文章や会話は将棋界以外でも人気がある。
- 注4 :
- 将棋界初の7冠を達成。タレントの畠田理恵さんと結婚し、マスコミでも大きく取り上げられた。
- 注5 :
- 1970年前後に生まれた世代で、羽生氏を中心に現在の将棋界の一大勢力となっている。森内俊之名人、佐藤康光棋聖、郷田真隆九段、丸山忠久九段、藤井猛九段など。
- 注6 :
- 順位戦はA級、B級1組、B級2組、C級1組、C級2組の5クラスに分かれており、10人いるA級の優勝者が名人戦の挑戦者となる。
- 注7 :
- 谷川氏が指す切れ味のいい鋭い攻めをこう呼ぶ。「光速流」ともいう。