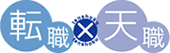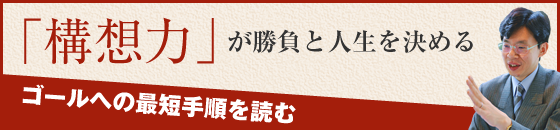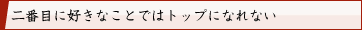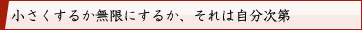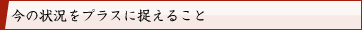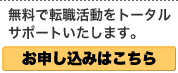谷川 浩司

プロフィール
1962年、神戸市生まれ。11歳で若松政和七段に入門し、14歳で4段となり、異例のスピードで昇進する。史上最年少21歳で名人、92年に4冠、97年には十七世名人になるなど、現在まで将棋界の第一人者として活躍している。

「構想力」
角川書店/
686円
棋士がA級に昇級したとき、それまでは上だけを見ていればよかったが、その後はB級へ落ちる心配をしなければならなくなる。たとえB級に降級しても1年で復帰することは珍しくない。だが、その機会を失い、しばらくB級に留まってしまうと、それがその棋士の実力となり、そのクラスの人間になってしまうという。
「人はそれぞれ恵まれている部分とそうでない部分をもっています。調子が悪いときはどうしても恵まれていない部分を見がちになるのです。うまくいかないときこそ、恵まれている部分を見るようにしないといけません。
また、自分は運が悪いと決めてしまう人もいます。将棋の場合、先手になるか後手になるかはまさしく運です。先手の勝率はおよそ5割3分で有利なのですが、先手か後手か、それに一喜一憂しても意味がありません。ある時期は先手が続いたり、その逆であったりすることもありますが、トータルでは五分五分なのです。
世の中にはいろんな要素があります。自分がベストを尽くしたからといって、必ず成功するとはかぎりません。自分の力ではどうしようもできない部分もあるのです。
運のいいときはありがたいと思い、悪いときは鷹揚にしているのがいいでしょう。貸しを作ったくらいに考えておき、それはいつか返してくれるだろうと。もっともよくないのは、責任転嫁をすることです。そうすれば努力しなくなりますから。
一般の社会において、将棋界でいうところのB級へしばらく落ちてしまったのなら、根本的な部分を変えてみるのも一つの解決策でしょう。転職を考えている人は、今の職場で一生懸命やったかどうかを自分に問うてみることです。一生懸命やったと自信をもって言える人は、仕事を変えてもいいのではないでしょうか」
米長邦雄氏は中学から高校までの6年間で、毎日5時間、合計1万時間、将棋の勉強をしたという。谷川氏も、中学2年でプロになるまでの約10年間で同じように1万時間を将棋の勉強に費やした。
「努力」という言葉で片づけるのは簡単だが、誰もが実践できるものではない。なぜ一流の棋士はそれほどまで勉強を続けることができるのか。
「ドイツに留学してメガネのマイスターとなっている友人がいます。彼などを見ていると、20代は専門技術の勉強に没頭していました。中にはやりたくない仕事もあるでしょうが、それは仕方ありません。10年で1人前になるといいますが、仕事についてすぐに給料をもらえることもどうなのでしょうか。
1万時間と聞けば、とても長い時間のように感じますが、1日3時間やれば、1年で1000時間、これが10年続けば1万時間になります。
最初のうちは30分でもいいのです。普段、出かける前の15分や20分は無駄に使っていませんか。それらの時間を有効に使ってもいいわけです。
試しに続けてみてください。続けられれば、それはおそらく自分にとって好きなことなのでしょう。
毎日続けていると、必ずといっていいほど壁にあたるときがきます。目に見える成果が出ないことが壁を感じる原因です。
それが、始めてから半年たっとときだったとしましょう。もし、そこで止めてしまえば、その半年間が無駄になってしまいます。辛抱してやり続けることで、飛躍的に伸びることができるのです。
私が将棋を続けることができたのは何より将棋が好きだったからでしょう。『一番好きなことを仕事にしてはいけない』といわれますが、二番目に好きなことではトップにはなれません。他のどんなことより好きでなければ、どうしても『一番』になろうとは思えないでしょうし、そのための創意工夫もできません」
史上最年少の21歳で名人位を獲得した谷川氏は、その2年後に名人位を失う。そのとき中学時代の担任の先生から「よかったな」と声をかけられている。
谷川氏はこの「よかったな」の意味を、最初の名人位は幸運に恵まれたが、次は実力で取りなさいと言われたとものと解釈した。
「将棋の場合、30歳がポイントになります。それまでに大舞台を経験していた人のほうが生き残れるようです。30歳を過ぎてから経験しても、それを活かしていくことは難しいのではないでしょうか。
ただし、誰もが大舞台に立てるわけではありません。後になって、もうちょっとやっておけばよかったと後悔しないためにも20代では研鑽を積んでおきたいものです。
昔、芹沢先生(注8)に可愛がっていただいたのですが、将棋盤は9かける9の81マスから成っています。『それを小さくするか、無限にするか、それは自分次第だ』と言われたことがあります。
20代のうちは少し生意気でもかまいません。ものわかりがいいだけというのもよくないのです。自分が一番強いと思っていても、若気のいたりと許してもらえます。小さく固まると、伸びしろがなくなるように思うのです。
将棋の世界でいえば、時代も変わってきていますから、服装が今風でも茶髪でもかまわないのでは。確かに伝統文化という面もありますが、ファンにアピールすることも大事です。
ただし、その分の責任はその人自身にありますし、中身がないとどうしても批判されます」
30代では大きな出来事に遭遇する。阪神淡路大震災だ。谷川氏は神戸出身で、現在もそうだが、震災当時も神戸に住んでいた。
この一件は人生を変えた。大地震は心までを大きく揺さぶったのだ。
「それまでは生きているのは当たり前のことだと思っていたのですが、(地震が)少しずれていたら命を落としていたかも知れないわけです。生きている部分と生かされている部分があることを知りました。
ファンの方からお見舞いや励ましをいただき、将棋は一人で指すものですが、いろんな人の支えがあって戦っていられるのだと再認識しました。
(被災地で活躍する)消防士さんは直接皆さんのためになっています。棋士である自分に何ができるのかを考えました。義援金の協力もしましたが、それで被災者の方々の生活が劇的によくなるわけではありません。でも、人々へのメッセージになりますし、自分への励みにもなりました。
21歳で名人になり、(20代は)大きな経験もしましたし、それが財産にもなりました。ただ、将棋だけでは半人前です。例えば、新聞に記事が載るのなら、社会面で扱われて一人前だと思います。
若いときは狭く深く、それが30代になれば、浅く広く全体的にものごとを考えるようになりたいものです」
最高齢で名人位に返り咲いたのは米長邦雄氏で、49歳11ヵ月のときだった。また、生涯の最多勝利の記録をもつのは大山康晴氏で、その数は1433勝。これらの記録の更新を谷川氏は現在の長期的目標としている。
「40代になっても体力的な問題はありません。ただし、ときどき集中力が途切れることがあり、つまらないミスをすることも増えてきました。でも、それを嘆いていても仕方がありません。
今の状況をプラスに捉えることです。つらかったりたいへんだったりすることは事実ですが、それを幸せだと考えるようにならないと。
棋士たちは対局を通して盤上で会話をしています。トップになれば会話の内容も豊富ですし、限られた人だけが理解できる世界なのです。その環境にできるだけ長くいたいと思っています」
- 注8 :
- 芹沢博文氏。最高位九段。タレント、文化人としても人気者だった。1987年、51歳の若さで死去した。