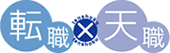転職×天職 > 半導体業界での転職 > PPM分析にみる日本半導体産業界のポジショニング20年史 > 第一回
![]() 日本の半導体産業が、世界レベルでその存在感を示し始めた時期は1980年代にさかのぼる。
半導体は、もともとアメリカで発明され発展してきた産業であり、それまではほぼアメリカが独占している市場であった。
日本の半導体産業が、世界レベルでその存在感を示し始めた時期は1980年代にさかのぼる。
半導体は、もともとアメリカで発明され発展してきた産業であり、それまではほぼアメリカが独占している市場であった。
しかし、日本でも、そのアメリカの牙城を切り崩そうと、1970年代後半から産官が協力して様々な試みに取り組んでいた。その代表的なものが「超LSIプロジェクト」である。
半導体産業には、高度な科学技術が要求される「知識集約産業」という側面と、それを製造するためには大規模な設備投資が必要な「装置産業」という側面がある。特に、後者については、大規模な工場設備を、半導体の性能が進歩するに従って定期的に更新していかねばならない宿命を背負った産業であるともいえる。
1970年代から80年代は、DRAMを中心とするメモリーの高集積化、微細加工技術の進歩が競われた時代であった。「トランジスタの集積密度は18ヶ月ごとに2倍になる」という「ムーアの法則」通りのスピードで半導体の性能は向上を続けていた。そのため、半導体産業の育成は、民間企業だけの課題ではなく、重要な国家プロジェクトと位置づけられて推進されたのである。
当時の資金で約700億円を投入した、この「超LSIプロジェクト」の研究成果を受けて、1980年代には日本の半導体はめざましい進歩を遂げていった。
当時の半導体メーカーは、いわゆる総合電機メーカーの半導体部門という形で存在していた。半導体専業メーカーが登場してくるのは後年のことである。製造される半導体は、基本的に自社製品に搭載されることを前提として開発されていた(一部外販もあった)。
特に、パソコンが一般化する以前の当時、大型コンピュータの市場は大きく、各社は自社製大型コンピュータの性能向上のために、半導体(メモリー)についても技術革新を競ったのである。結果的に、このことが日本製半導体の進歩に大きく寄与したといわれている。自社の大型コンピュータに搭載するというアプリケーションが明確であったこと、そして全工程を自社内でまかなう垂直型の開発形態をとったこと…などによって高集積化、微細加工といった技術開発のスピードアップと大幅な品質向上が実現されたのである。
とりわけ、半導体製造の現場で重要な歩留まり率で、日本メーカーは世界水準を大きくリードすることになった。歩留まりが改善されれば価格も抑えられる。製造プロセス重視は、半導体業界にとどまらず日本の製造業のお家芸ともいえるものだが、ここでもその生産技術・品質保証技術の高さが世界に示された形となった。
この高品質・低価格を背景に、日本の半導体は世界で大きなシェアを占めるようになる。1970年代まではインテルなどアメリカ企業の独壇場であった世界の半導体市場で、日本製半導体は、実に50%もの占有率を誇るまでに成長した。IBMやヒューレット・パッカードなど大手コンピュータメーカーも日本製のDRAMを採用。ついには、1986年、世界の半導体メーカー上位10社のうち6社を日本のメーカー(NEC、東芝、日立、富士通、松下、三菱電機)が占めるに至るのである。まさに、日本半導体業界の黄金期ともいえる時代の到来だった。
しかし、良い時代は長くは続かなかった。これによりシェアを奪われたアメリカは激しい危機意識を持つことになったのである。最先端技術である半導体産業は軍需産業の一部と見なされており、国家戦略的にも日本に負け続けることは許されないことだったのだ。
また、同時期に日本メーカーがさらなるシェア拡大を狙って行った価格引き下げは、アメリカ国内でダンピング(不当廉売)ではないのかという声を高めることになってしまった。これらにより事態は日米半導体摩擦へと発展していくのである。
1986年、ダンピングの防止や外国製半導体の日本でのシェア拡大をうたった日米半導体協定が締結された。しかし、アメリカはそれだけにとどまらず日本製のコンピュータや家電製品などに報復関税をかける対日経済制裁を実施。また、米国内では産官学の連携プロジェクトである「セマテック」を発足させる。これらにより、アメリカの半導体業界は、本格的に日本追撃の態勢を整えはじめるのである。