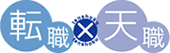転職×天職 > 半導体業界での転職 > PPM分析にみる日本半導体産業界のポジショニング20年史 > 第二回
1980年代中盤、世界シェアの50%を獲得するという輝かしい実績をあげた日本の半導体産業だったが、日米半導体摩擦をきっかけに巻き返しを図るアメリカ勢の前に、しだいに身動きの取れない状況に追い込まれていくことになった。
まずアメリカは、日米半導体協定に基づく「フェア・マーケット・バリュー(FMV)」により、DRAMの価格を一定以下に下げないことを徹底させる作戦に出た。製造プロセスの改善、歩留まり率の向上などの独自技術によって、高品質の製品を低価格で供給してきた日本の半導体メーカーにとって、これは厳しい足かせとなった。
価格面で日本勢の動きを封じながら、アメリカは同時に、半導体技術そのものについても競争力を回復すべく、産官学の連携プロジェクトである「セマテック(SEMATECH・SEmiconductor MAnufacturing TECHnology)」を立ち上げる。
これは、アメリカ国防総省と民間の半導体大手企業、及び大学が協同した研究開発プロジェクトであり、1970年代の日本における超LSIプロジェクトを意識したものであったともいわれる。セマテックの初代会長は、当時のアメリカ半導体業界のリーダーであったインテルの会長が務めた。いずれにしても、アメリカが国家レベルで半導体産業をてこ入れする意思を示した画期的なプロジェクトであったといえる。
セマテックは、様々な技術開発を行ったが、その中心になったのは、やはり日本メーカーの強みといわれた高集積化、微細化技術に対応する生産技術、とりわけ品質管理の技法を徹底的に研究することだった。
それによって、日本メーカーのTQCをさらに発展させ、数値レベルで品質管理を行う「TQM」や、全員参加で生産設備の管理を行う「TPM」などが編み出された。またTI(テキサスインスツルメンツ)社が中心になって開発した「MES」は、情報システムを生産現場に導入することによって、これまでにかった低コスト生産技術を実現させた。
ユニオン(組合)の関係で、エンジニアが生産現場に立ち入ることがほとんどなかったアメリカでは、まさに革新的といわれたこれらの技法だったが、やがて世界の半導体業界の標準になっていく。
とはいえ、1990年代の初頭は、日本の半導体業界にとっては、まだまだ善戦が続いていた時期ではあった。 価格面の優位性がやや失われたことによって、三星など韓国メーカーにシェアを奪われた部分はあったが、高品質な日本製DRAMは、依然として世界一の座を保っていた。
この優位が本格的に崩れたのは、半導体のコアマーケットが、大型コンピュータからPC(パソコン)へと移行したことが要因だった。1990年代に入ってのインターネットの普及、マイクロソフトによるウィンドウズの発売などにより、世界のコンピュータ需要に大きな地殻変動が生じたのである。
その結果、1980年代に大型コンピュータで要求された高品質な半導体よりも、PC向けの安価に大量生産できる半導体の需要が爆発的に高まることとなった。
この流れにスムーズに対応できたのは、セマテックでの研究を通じて、低価格・量産化技術に磨きをかけていたアメリカ製、そしてその技術を導入していたアジア製(韓国、台湾など)だった。
生産手法が進化した結果、半導体においても水平分業が発達してくる。設計のみを行うファブレスメーカー、生産受託のみを行う工場、パッケージングやテストのみを行う企業…など、それぞれ得意分野に特化した企業が、国境を超えて連携を始めた。それによって、コモディティ化した半導体の低価格化はさらに進むことになる。
また、インテルをはじめとするアメリカ企業のなかには、価格競争の色合いの強いDRAMから、より付加価値が高く、高収益が見込まれるMPUなどの分野にシフトする企業も現れはじめていた。 それに対して、日本の半導体メーカーはこの流れを読めていなかったといえるだろう。 1980年代の成功体験から脱却できなかったのである。日本勢は、独自の高品質な製造プロセスにこだわり続け、価格的な競争力を完全に失った。
1993年には、アメリカに抜かれ世界シェアは2位に転落したが、総合電機メーカーの半導体部門という組織のあり方が柔軟な対応を困難にしていた。世界は、分業化された半導体専業メーカーの時代に入っていたにもかかわらず、日本は企業も、そして政府(国)もこの状況に流されていただけだったのである。
先の見通せない日本の半導体業界の低迷期は1990年代いっぱい続くことになる。