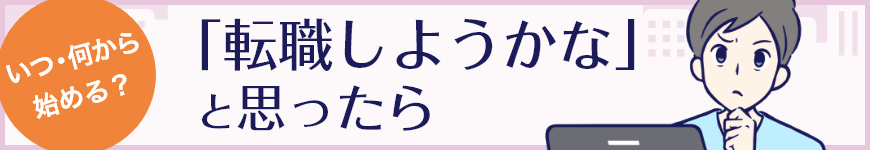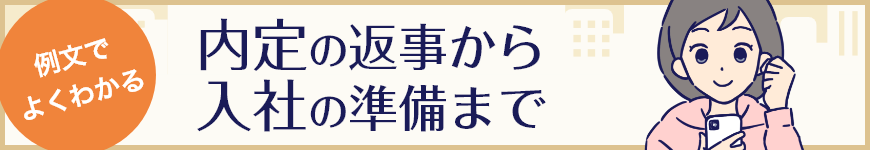「雇用契約書なし」の会社は危険 残業代も賞与も出ない?実際のトラブル事例
雇用契約書や労働条件通知書などの書面で、労働者に雇用条件を通知するのは会社の義務。「これすら守らない会社は危ない」と労働問題に詳しい弁護士の鈴木悠太さんは言います。
雇用契約書や労働条件通知書がないことでどんなトラブルが起きているのか、実際の事例を聞きました。
事例1 固定残業代について説明しない会社
Aさんは「月給30万円」という求人広告を見て、イベント会社に中途入社しました。部署は管理部門。
雇用契約書も労働条件通知書も受け取っていませんでしたが、入社当初は残業もなく、毎日定時の18時に退社、毎月の給与も額面で30万円が支払われていました。
ところが、入社して8カ月目から業務が急に忙しくなります。連日20時頃までの残業が続き、日によっては22時過ぎまで残業することも。月の残業時間は50時間を超えましたが、なぜか給与は額面30万円のままでした。
当然、残業代が支払われると思っていたAさんが上司に問い合わせると、「月給30万円には固定残業代が含まれており、残業をしてもしなくても給与は変わらない」という説明を受けたのです。
「採用面接では、確かに基本給30万円と言われました」とAさんが訴えても、「キミの勘違いだよ」と上司が出してきた就業規則には「給与月額30万円(一律残業手当を含む)」と記載されており、Aさんの主張は聞き入れてもらませんでした。
解説|残業代は最もトラブルが起こりやすい
鈴木悠太さん(以下、鈴木):労働条件の書面通知がない場合、最もトラブルになりやすいのが「残業代」です。残業代については、労働者側も就業前に確認しないケースが多く、残業代に関する労働条件が書面として何も残っていない場合、労働者が泣き寝入りする事例が多く発生しています。
中でも、固定残業代は特にトラブルの原因になりやすいと言えます。
固定残業代は「○○時間残業したとみなして支払われる」もので、あらかじめ毎月支払われる固定給の中に含まれている残業代です。みなしの残業時間を超えて残業が発生した場合、会社は追加の残業代を支払わなければならず、Aさんの上司が言ったような「定額働かせ放題の制度」ではありません。

しかも、Aさんの場合、固定残業代といっても、残業代はいくらなのか、何時間分の固定残業代なのかが明記されていませんでした。こうしたケースでは固定残業代は無効とされる可能性があります。
Aさんのケースでは、あきらめずに弁護士に助けを求めた結果、なんとか一定の残業代を支払ってもらうことができました。
私たち弁護士が「固定残業代の定義があいまいだったこと」「就業規則を労働者に見せるタイミングが遅すぎたこと」などを厳しく追及したことで、会社側も残業代を支払わざるを得ないと判断したようです。
事例2 支給されない賞与を含んだ「見込み年収」の罠
Bさんは転職時の採用面接で、「見込み年収は480万円です」と告げられました。
その内訳は、毎月の基本給が30万円で年間360万円、6月と12月に賞与がそれぞれ基本給2カ月分支給されて30万円×2カ月×2回=120万円とのことでした。
その後、会社側から採用内定をもらったBさんは、「年収480万円なら」と入社を決意。しかし、労働条件が書面で通知されることはありませんでした。
基本給は当初の説明通り毎月30万円が支給されましたが、年収は480万円には届きませんでした。入社から1年以上が経ち、賞与の支給対象期間を満たした後も、期待していた賞与が支給されることはなかったのです。
不審に思い、上司や総務に問い合わせたところ、「業績が悪化したので賞与は支給されません。面接で伝えた年収は、あくまでも“見込み”です」との回答。結局、入社前にアテにしていた年4カ月分のボーナスは支給されず、Bさんの年収は転職前より少なくなってしまいました。
解説|賞与のトラブルは労働者の主張が通りにくい
鈴木:賞与については労働条件通知書に記載がある場合でも、しばしばトラブルが起こります。たとえば「毎年6月と12月の2回、基本給の2カ月分を支給する」と支給額まで明記されていれば問題ないのですが、ほとんどの場合は「年に2回、6月と12月に支給する」といった程度にしか書かれていません。
賞与は業績に応じて支払う会社が多く、その金額は使用者(会社)の裁量に任されていて、労働者側の言い分が通りにくいと言えます。Bさんのケースでは、証拠がないため会社が賞与や見込み年収についてどのように説明したのか証明することができません。
いずれにしても、採用が決まって働き始める前に給与などの労働条件を書面で確認しておくことが大切です。
事例3 正確な労働条件を明示しなかった会社に慰謝料を請求
Eさんが損害保険会社Y社に中途入社したのは、Y社の求人広告に次のような内容が書かれていたからです。
「やり直したい方募集。ハンディはなし。たとえば1989年卒の方なら、1989年に新卒入社した社員の現時点での給与と同額をお約束します」
Eさんは1981年に新卒であるメーカーに就職していましたが、今Y社に中途入社すれば、1981年に新卒入社した社員と同額の給与がもらえるというのです。
ところが、実際にEさんに支給された給与は思いのほか低いものでした。Eさんは、1981年に新卒入社した社員の現時点での平均的な給与額が支給されると思っていたのに、実際に支給されたのは、1981年に新卒入社した人の最も低い水準の給与額だったからです。
Eさんがその事実を知ったのは、入社して1年後でした。「これでは話が違う!」と憤ったEさんは、平均的水準の給与との差額分と慰謝料の支払いを求め、裁判所に提訴しました。
解説|裁判で慰謝料の支払いが命じられたケース
鈴木:Eさんの立場からすれば、Y社が求人広告で謳った労働条件は実際の労働条件と異なるものでした。Y社は労働条件の明示義務に違反したのだから、求人広告で謳った分の給与と慰謝料を支払ってほしいと訴えたわけです。

この裁判は、企業の労働条件明示義務違反が実際の裁判でどう判断されるか、多くの法曹関係者の注目を集めました。
判決は、差額分の給与支払い請求については棄却したものの、「Y社は労働条件の明示義務に違反しており、雇用契約締結時における信義誠実の原則に反するという不法行為が成立するため、Eさんに慰謝料100万円を支払え」というものでした。
この裁判は、「使用者が正確な労働条件を明示しなかったことで労働者に不利益が発生した場合、使用者は労働者に対して慰謝料を支払う」ことの先例となりました。
事例4 コロナ禍で休業させた従業員を補償しない飲食店
鈴木:この後に紹介する2つの事例は、ややイレギュラーなものですが、労働条件について書面に明示しておくことの重要性がよくわかるケースと言えます。トラブルを未然に防ぎ、ご自身の身を守るためにも知っておいてください。
Cさんは飲食店のホールスタッフとして働いていました。シフト制で時給は1,200円、週4日程度の勤務という条件で、毎月12〜16万円の収入を得ていました。収入に幅があるのは、他のスタッフのシフトとの兼ね合いで、シフトが減らされる週もあったためです。
その店はスタッフ同士仲が良く、とても働きやすかったので、Cさんはできるだけ長くこの仕事を続けたいと思っていました。
ところが、折からのコロナ禍で来店客が激減。ある日突然、店側からCさんに休業命令が出されました。「業績悪化のため休業してください。当面の間、あなたのシフトはゼロです」と店長から伝えられたのです。
いきなり収入の道を断たれたCさんは、「週4日でシフトに入っていたので、その分の休業補償をしてほしい」と店側に訴えました。
しかし、Cさんはこの店で働くにあたって、明確な労働条件を確認しておらず、店側は「週4日はあくまで目安であり、その分の収入が保障されていたわけではない」と主張、休業補償は拒否されてしまいました。
解説|シフト制はトラブルが発生しやすい勤務体系
鈴木:2020年春以降、飲食業界はコロナ禍で大打撃を受け、飲食店の雇用状況は急速に悪化しました。そのため、Cさんのように今まで通り働けなくなって生活に困窮する人が続出、ニュースなどでも大きく取り上げられました。
シフト制は雇用契約書や労働条件通知書に就業時間を明記しにくいため、もともと労働トラブルが発生しやすい勤務体系と言えます。ましてやCさんの場合、正式な雇用契約書や労働条件通知書を受け取っていないため、「週4日勤務する権利がある=週4日分の給与を受け取る権利がある」ことを会社側に認めさせにくいのです。
Cさんの場合は、過去数カ月にわたって週4日ペースで働いていた記録が残っていたので、その数字をベースに弁護士が会社側と交渉し、平均賃金の6割にあたる休業手当を受け取ることができました。
事例5 激務でうつ病になったのに雇用関係さえ認めない会社
会社を辞めて転職活動中だったDさんに、Web制作会社のZ社から仕事の依頼がありました。Dさんは2年前までZ社で経理担当として働いており、「帳簿作成業務が滞っているので力を貸してほしい」と社長から直々に頼まれたのです。
出社の必要はなくオンラインで作業すればよいということ、そして「作業量に見合う給与はちゃんと払うから」と社長に言われたことから、Dさんは依頼を受けることにしました。
しかし、それは想像以上に大変な作業でした。Dさんの退社後、経理業務がかなり杜撰になっていたようで、膨大な量の請求書や領収証などが未整理のまま放置されていたのでした。
Z社から日々送られてくる大量のデータを処理するため、Dさんはほとんど自宅PCの前から動けない状態に。作業はしばしば夜遅くまで及び、Z社の就業時間に合わせて計算すると、残業時間は毎月100時間を超えました。
誰からも応援やサポートを受けられないまま、日々大量のデータと格闘し続けたDさんは、やがて体調に異常を感じ始めます。
疲れているのに眠れない。ようやく眠りに就くと今度は朝起きられない。食欲はまったくなく、頭痛・耳鳴り・めまいがする。自分でも「これはおかしい」と気づき、総合病院で受診した結果、「うつ病」と診断されました。
そこでDさんは労災保険の給付を申請することにしました。しかし、Z社は「労働災害ではない。DさんはZ社が雇用している労働者ではなく、業務委託を受けた個人事業主だ」と主張して異議を唱えたのです。
解説|労基署も「雇用関係が成立していない」と判断
鈴木:Dさんが発症したうつ病は、明らかにZ社での苛酷な労働が引き金になっています。そのためDさんは、労基署に労災申請をしましたが、労基署は労災だと認めませんでした。
DさんはZ社から雇用契約書も労働条件通知書も受け取っておらず、何より、DさんとZ社の間では就業時間や賃金などの取り決めもまったくなされていなかったため、「そもそも雇用契約自体が成立していない」と判断されたのです。
Dさんのケースは、就業前に「雇用契約の成立」と「労働条件」を確認することがいかに大切かを、改めて示すものになりました。
労働条件を書面通知しない会社は避けるべき
鈴木:労働条件の書面通知は会社の義務であり、労務管理の「基本のキ」です。これすら守らない会社は、労務管理がきわめて杜撰で、いわゆるブラック企業の可能性さえあるでしょう。
入社する前に労働条件の書面通知があるか必ず確認しましょう。もし書面通知してもらえない場合には、入社を辞退するのが賢明な選択といえます。
すでに働き始めてしまっている場合は、すぐに労働条件を書面で明示してくれるよう会社に求めましょう。もし、会社に対応してもらえそうにない場合は、労働条件に関する何らかの証拠を残しておきましょう。
たとえば、ICレコーダーで「労働条件に関する約束」を録音しておく、メールで労働条件について問い合わせて、その記録を残しておくといった方法が考えられます。将来的なトラブルを回避するために、面接などの内容を個人的に録音しておくことは問題になりません。
もし会社とトラブルになった場合には、個人加盟の労働組合や労働者側の弁護士など、労働問題の専門家に相談しましょう。
※参考→雇用契約書・労働条件通知書の意味(雇用契約書等が示されなかったら)|Blog「弁護士が教える分かりやすい労働法!」(鈴木悠太)
取材・文/盛田栄一
この記事の話を聞いた人

弁護士
鈴木悠太
旬報法律事務所
一橋大学卒業、一橋大学院法学研究科修了。人の人生に寄り添う仕事がしたいという思いから弁護士を志す。ブラック企業被害対策弁護団副事務局長、医療問題弁護団幹事などを歴任。年間100件近くの労働事件を扱う労働問題のプロフェッショナル。